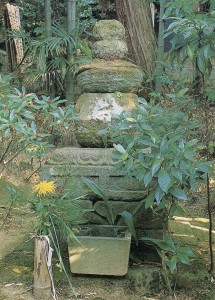神奈川と親鸞 前編21回
神奈川と親鸞 第二十一回 筑波大学名誉教授 今井 雅晴
鎌倉での一切経校合⑴ 一切経とその校合とは
覚如の『口伝抄』に、親鸞が執権北条泰時の依頼で一切経の経合を行なったとある。第二次大戦後の長い間、これは覚如の作り話だろうとされてきた。理由は、親鸞は庶民の味方、庶民を圧迫する権力者の仕事を手伝うはずがない、ということであった。しかし親鸞が信奉した阿弥陀仏は庶民だから救う、権力者だから救わないなどと説いてはいない。すべての人々を救う存在のはずである。当然、親鸞もすべての人々に救いを説いたであろう。
近年では親鸞の一切経校合は事実だったのではないか、という見方が広まりつつある。この連載では、すなおに『口伝抄』の記事とそれに関わる周囲の状況を検討していきたい。
一切経というのは何であろうか。一切経という名称の経典があるのではなく、経典一切、すべての経典という意味である。大蔵経と同じである。大蔵経も経典名ではない。
一切経には、釈迦の教えを記した「経」と、修行者の集団(サンガ)を維持するための罰則の「律」、それらの解説書の「論」、そして「経」「律」「論」の注釈書も含まれている。一切経の目録では、中国の唐の貞元十六年(西暦八〇〇年)に完成した『貞元新定釈教目録』がもっとも尊重されてきた。そこには五千巻近くが収められている。朝鮮の高麗で出版された『高麗八万大蔵経』(高麗大蔵経)も日本に影響を与えている。
一切経作成のためには、多数の経典類を書写する必要があるし、その前に同じ経典を多く集めて誤字・脱字等を正さねばならない。経典類は書写を繰り返しているので、誤持・脱字等が生じがちだったからである。これを正す作業が校合である。そのためには広い知識と優れた識見が必要である。その上での一切経書写と奉納は、大事業であるがゆえに仏の大きな恩恵が期待された。その恩恵とは国家防衛・国家安定であった。
日本においても一切経書写や奉納は奈良時代から行なわれている。その際には、国家安定を意識しつつも、身近な人の追善供養が主な目的となっていた。
北条泰時はその一切経奉納事業を企て、親鸞が校合を担当したということである。